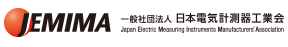1-1-6-4 水分計
水分計とは、物質に含まれている水分の量を測定する計器である。気体・液体・固体といった物質中に含まれている水分量は見た目では分からないため、水分計を使って水分量を測定する必要がある。
水分計の種類は「電気信号」と「光出力」の二つに大別できる。
「電気信号」を利用する水分計には、電気抵抗式や電気容量式などが代表的である。測定方法は、水分を測ろうとする測定対象に対して電流を流すことで得られる電圧値から、電気抵抗値や電気容量を測定する仕組みになる。電気抵抗式の場合は比重に影響しないメリットがあるが、測定対象を傷つけることになるので今ではほとんど使用されていない。反対に、世界でも幅広く使用しているのが電気容量式になる。電気容量式は測定物に交流の電流を流して電気容量の変化を水分値に置き換える方法になる。デメリットとしては電気抵抗式と比較して精度が良くないことが挙げられる。
「光出力」を利用する水分計は光の吸収度合いを調べる方法になる。光を使用した測定方法には種々の方式があり、「近赤外式」「中性子式」「乾燥重量法」「化学測定法」などがある。たとえば、「近赤外式」は1.43μmや1.93μmの波長を持つ光を利用している。この波長域は水分への吸収率が非常に高いため、反射率の測定によって水分量を測定する仕組みとなり、水分が多ければ多いほど反射する光が弱くなる。そして、乾燥重量法は対流式乾燥機で絶乾状態にした対象物の重量変化から水分量を測定する仕組みとなる。精度は高いが、測定時間や手間がかかるなどデメリットもある。また、測定対象が水のみであれば、化学測定法は正確な測定が可能である。
分光特性グラフと吸収強度(ランベルト・ベールの法則)
特定波長の赤外線は分子(原子)に吸収される特性を持っている。この波長はその分子を構成する原子やその結合状態により吸収される波長が異なる。
下に示すグラフは、赤外線の吸収(透過率)を縦軸に、波長(µm)を横軸にして表した分光特性グラフの一例である。
水の吸収特性や、溶剤、フィルム、油など、それぞれ違った特性を表している。また、この吸収特性は、その物質の量(厚み)に応じて吸収が強くなる。これはランベルト(ランバー)・ベールの法則として表される。
株式会社チノー ホームページ(URL:https://www.chino.co.jp)より参照