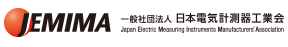1-1-6-3 湿度・露点計
湿度の測定方法にはいろいろある。以下にいくつか代表的なものを紹介する。
- 乾湿球形湿度計
「乾湿球形湿度計」とは、2本のガラス製の温度計の一方にガーゼ(ウィック)がついた湿度計である。これは、温度を測定する乾球温度計と、感温部にガーゼ(ウィック)を巻き、そのガーゼ(ウィック)を湿らすための水を入れる水つぼが取り付けられた湿球温度計で構成され、湿度はこの2本の温度計の乾球温度と湿球温度との温度差により算出されます。湿球温度は、ガーゼ(ウィック)から水が蒸発して気化熱が奪われるため、乾球温度より低下する。水の蒸発は接している空気の相対湿度により異なり、相対湿度が100%であれば水は蒸発しない。(参考:湿球温度換算表)「乾湿球形湿度計」は、湿度20%くらいからの測定になり。乾湿球形湿度計は、ガーゼ(ウィック)の取り扱い、十分な通風、水質、温度変動等で誤差を生じる。 - 通風形乾湿球湿度計
アスマン形通風乾湿計が代表である。感温部に強制的に3~5m/秒の風を送り、より正確に湿度測定が行えるようにしたものを「通風形乾湿球湿度計」と呼び、ガラス製温度計に換えて白金測温抵抗体などを使い電気信号を取り出すものを「電気式湿度計」と呼ぶ。 - 電子式湿度計
工業界で広く使用されている湿度計で、電子式湿度計は主に、電気抵抗式と静電容量式に分類される。どちらも水蒸気の吸着を利用しており、この水蒸気の吸着は相対湿度が高いほど吸着量が増加する。水蒸気の吸着量を電気抵抗の変化や静電容量の変化を測定して湿度に変換している。 - 電気抵抗式
電気抵抗式は、相対湿度によって湿度検出素子の抵抗値が変化する湿度素子が使用されていまる。相対湿度が高いほど抵抗値は低くなる。20%RH以下の低湿度では誤差が大きくなり測定不可能になることや高温では素子が劣化する。 - 静電容量式
静電容量式は、高分子膜の両面に、真空蒸着によって薄い網目状の電極を設けた形態になる。つまり、水蒸気が電極を通して高分子膜に吸着すると、この電極間に電気を蓄え、その電気容量(静電容量)の変化をとらえるというしくみである。高分子膜が吸収あるいは放出する水分量は測定する雰囲気の相対湿度に比例するので、この吸湿水分量の変化を誘電率の変化としてとらえ相対湿度を測定する。 - 露点温度計(光学式)
現在、最も正確に湿度を測定できる方式である。測定する気体を冷却した鏡の上に導入し、鏡のくもりを光の反射で検出する。鏡が曇り始めるときの鏡の温度を正確に測定することで、露点温度tdを直接測定する。また、測定する気体の温度を別に測定しておけば、測定された温度、露点温度から相対湿度への変換も可能になる。光学式露点温度計は、電子式湿度計の基準器として利用される。株式会社チノー ホームページ(URL:https://www.chino.co.jp)より参照